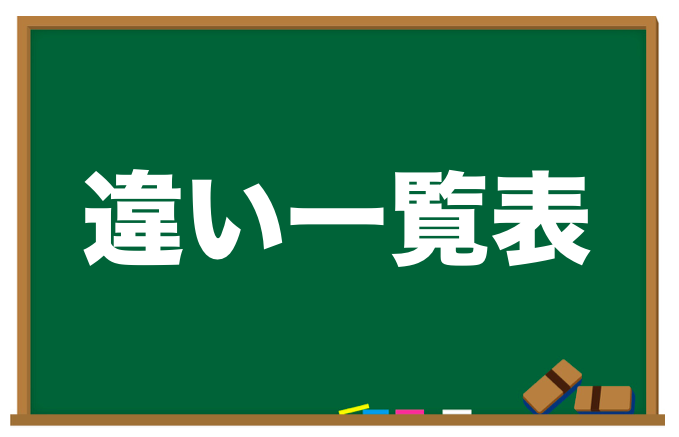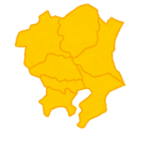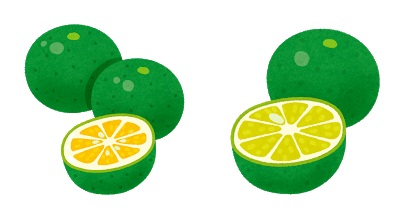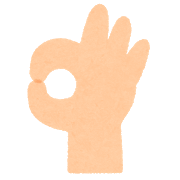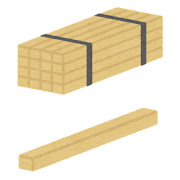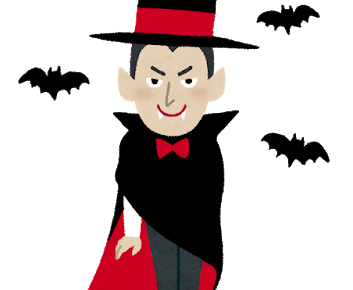秋になると脂がのっておいしくなる鮭。
漢字で書くと「鮭」ですが、「サケ」と「シャケ」、2通りの表記がありますね。
どちらが正しいのでしょうか?
おにぎりの具は、「シャケ」と表記しているものが多い気がします。
でも、「鮭茶漬け」は、普通「シャケ茶漬け」とは言いませんよね?
今回は、この「サケ」と「シャケ」の表記や呼び方の違いについて、様々な側面からアプローチしてみました。
「鮭」についておさらいしてみよう

サケ(出典:Wikipedia)
はじめに「鮭」という魚についておさらいを。
鮭は、川で産まれ、幼少期を河川で過ごしながら成長し、外洋に出ます。
3~5年海を回遊して成熟すると、自分の生まれ育った川に戻ってきます。
これを「母川回帰」というのですが、このメカニズムは、いまだに詳しくは解明されていないそうです。
鮭が川の流れに逆らって上流に上っていく姿は、いたましいような感動を覚えますね。
そして、一度受精の役割を果たすと、力尽きて死んでしまいます。
これは、100尾の稚魚を放流すると約4~6尾の鮭が戻ってくるという計算です。
途中で捕食されたり、死んだりすることを考えると、とても多いと思いませんか?
また、鮭は赤身の体をしていますが、分類学上は白身魚の一種です。
あの赤い色は、アスタキサンチンと呼ばれる色素が、鮭の肉に含まれているためです。
アスタキサンチンは、体にたまった活性酸素を除去してくれる「抗酸化力」をもつ成分として注目されています。
「鮭」は「サケ」か?それとも「シャケ」か?

鮭の刺身(出典:Wikipedia)
それでは、「鮭」は、どうして「サケ」や「シャケ」と呼ばれるようになったのか?また、どちらが正しいのか?についてお伝えしてきますね。
「鮭」が「サケ」と呼ばれるようになったわけ
「鮭」が「サケ」という名前で呼ばれるようになったわけとしては、
- 肉質が軟らかく、裂けやすいために「裂け」→「サケ」
- 肉の色が赤くて酒に酔ったようであるために「サカケ」→「サケ」。赤色を示す朱(アケ)がサケに転じたという説も
- 東北で大きな魚を表す方言である「スケ」という言葉が転じて、「サケ」になった
- アイヌ語でマスを意味する「サキペ」を、和人が混同して「サケ」と呼ぶようになった
など様々な説があります。

「鮭」が「シャケ」と呼ばれるようになったわけ
江戸時代のいわゆる「江戸っ子」といわれる人たちは、「サシスセソ」の発音が苦手でした。
「七」を指す「しち」が言えなくて「ひち」になってしまう、などという話は聞いたことがありますよね?
そのため、「サケ」よりも発音しやすい「シャケ」が、通称として全国に広まったという説があります。

加工の仕方によって区別されている?

また、生きている鮭は「サケ」、死んで加工された鮭は「シャケ」として分類されているという説もありますが、これはどうも眉唾ものです。
「シャケフレーク」もあれば、「サケフレーク」もありますし。
確かに、「塩鮭」「荒巻鮭」などのように、「鮭」の前に修飾語がつく場合は、「塩ザケ」よりは「塩ジャケ」、「荒巻ザケ」よりは「荒巻ジャケ」の方が発音しやすいですよね?
でも、「鮭茶漬け」は、「シャケ茶漬け」よりも、「サケ茶漬け」の方が言いやすいのでは?
どうもこの2つの区別の仕方って、前後につく言葉との関係や、慣用的に「シャケ」が使われている地域とそうでない地域という違いであって、どちらが正しいというものではないような気がします。
「サケ」と「シャケ」の違いまとめ

- これまで書いてきたことを簡単にまとめてみますと、
- 「サケ」と「シャケ」は同じ魚を指している
- 加工によって使い分けているという説もあるが、商品名などで徹底されているわけでない
- 呼びやすさや、慣用的に使われてきたかどうかの差によるものが大きい
いかがでしたでしょうか?
テレビのニュースなどで読み上げられる場合は「サケ」が多いようですが、話し言葉としては「シャケ」も色々な場面で使われているということですね。